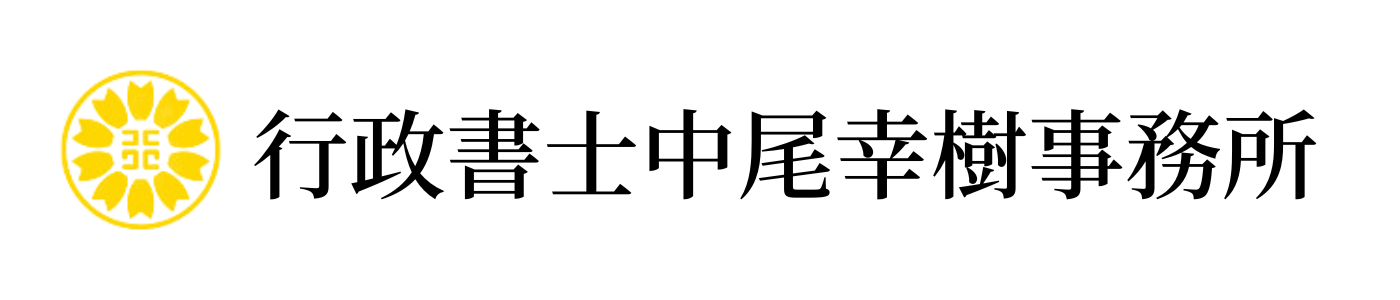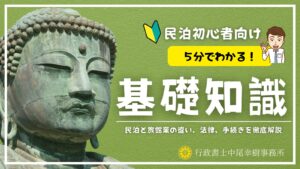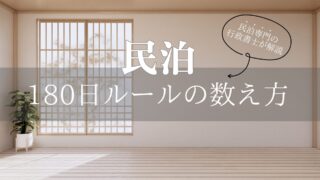
「民泊をはじめたいけど、180日ルールって何だろう?」「違反したらどうなるの?」と不安を抱えていませんか?民泊は空き部屋を有効活用できる魅力的な投資方法ですが、法律の壁に戸惑う方も少なくありません。特に「年間180日しか営業できない」というルールは、収益計画に大きく影響します。
この記事では、民泊新法(住宅宿泊事業法)による180日の営業制限について、わかりやすく解説します。違反した場合の罰則から対応策まで、私たち行政書士がサポートできるポイントを含めて詳しくご紹介。法律の専門家だからこそお伝えできる情報で、あなたの民泊ビジネスを安全に、そして最大限に活かす方法をご案内します。
この記事を読むとわかること
- 民泊新法における180日ルールと数え方
- 180日ルールに違反した場合の罰則と行政の監視体制
- 180日制限に対応するための具体的な対策
- 行政書士に相談するメリットと無料相談の活用法
- 1. 民泊180日ルールの背景と法的意義
- 1.1. 民泊新法が制定された社会的背景
- 1.1.1. ホテル業界との棲み分けと規制の違い
- 1.1.2. 住環境保護の観点から見た180日制限
- 2. 民泊180日ルールとは?基本と具体的な数え方をわかりやすく解説
- 2.1. 民泊新法(住宅宿泊事業法)における180日の定義
- 2.1.1. 具体的な営業日数の数え方と注意点
- 2.1.2. 自治体による追加規制の具体例
- 3. 180日ルールに違反した場合の罰則と注意点
- 3.1. 旅館業法違反としての罰則内容
- 3.1.1. 民泊新法(住宅宿泊事業法)としての罰則
- 3.1.2. 近隣通報による追加罰則
- 3.1.3. 監視体制と自治体による取り締まり状況
- 4. 民泊180日ルールへの対応策・打開策
- 4.1. 特区民泊の活用
- 4.2. 旅館業許可(簡易宿所)の取得
- 4.2.1. マンスリーマンションとの併用区分
- 5. 行政書士による民泊届出サポートのメリット
- 5.1. 複雑な申請手続きを正確に行うための専門知識
- 5.2. 自治体ごとの規制対応と最新情報の提供
- 6. 民泊オーナーからよくある質問と回答
- 7. まとめ:行政書士に民泊届出を相談するメリット
民泊180日ルールの背景と法的意義
民泊新法が制定された社会的背景
民泊新法が2018年に施行された背景には、インバウンド観光客の急増とホテル不足という社会的要因があります。一方で、無秩序な民泊の増加によって、騒音問題やゴミ出しルール違反など、住環境の悪化も問題となっていました。
民泊の180日制限(住宅宿泊事業法)の背景は以下の3点に集約されます。
- 住環境の保護: 住宅地での民泊による騒音やゴミ問題など、近隣住民の生活環境への影響を最小限に抑えるため、年間営業日数を180日に制限。
- ホテル業界との棲み分け: 旅館業法に基づくホテル・旅館との競合を避け、観光需要と既存産業のバランスを取る。
- 観光振興と規制の両立: 訪日客増加に伴う宿泊施設不足を補いつつ、違法民泊を防ぐため、適度な規制を設けて民泊を合法化。
ホテル業界との棲み分けと規制の違い
民泊とホテルや旅館など既存の宿泊業との大きな違いは、「住宅」としての性質を残している点です。旅館業法による宿泊施設(ホテル、旅館、簡易宿所)は年間営業日数の制限がなく、専用の施設として運営されます。
一方、民泊新法による民泊は、本来は「住宅」であることを前提としており、そのため180日という制限が設けられています。この制限により、既存宿泊業との競争を緩和し、市場の棲み分けを図っているのです。
なお、当初民泊で事業を始めたとしても旅館業法の簡易宿所の許可を取得すれば、年間営業日数の制限なく営業することも可能です。ただし、建築基準法上の用途変更や消防設備の設置など、用途地域や住民協定など、旅館業法の厳格な基準をクリアする必要があります。
住環境保護の観点から見た180日制限
民泊新法における180日制限のもう一つの重要な目的は、住環境の保護です。一般の住宅地に観光客が頻繁に出入りすることで生じる問題(騒音、セキュリティ、ゴミ問題など)を緩和するため、営業日数を制限しているのです。
民泊オーナーとしては、180日という制限をデメリットと捉えるのではなく、「住宅地での営業を認めてもらうための条件」と前向きに考え、その中で最大限の収益を上げる工夫をすることが大切です。
民泊180日ルールとは?基本と具体的な数え方をわかりやすく解説
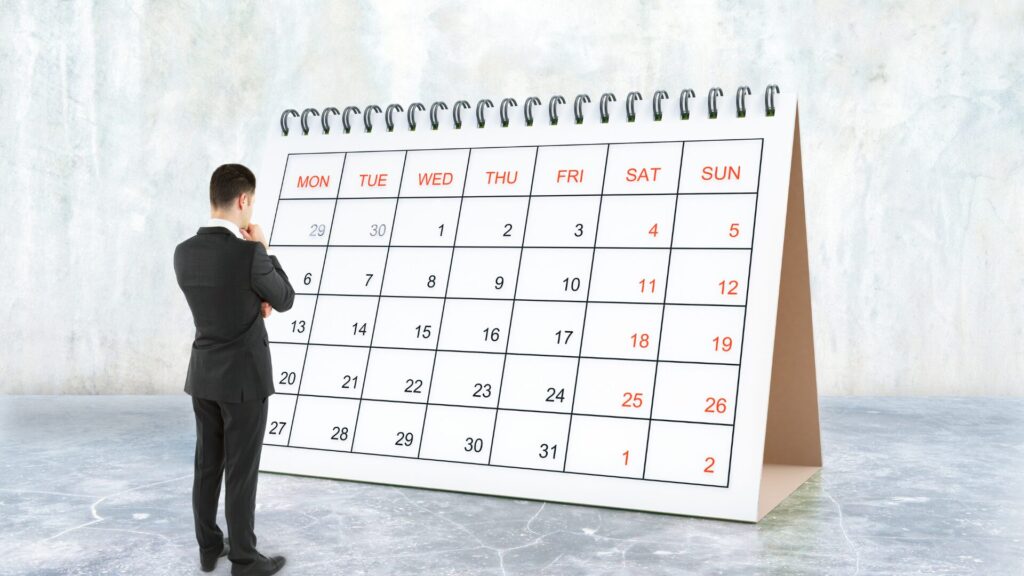
民泊新法(住宅宿泊事業法)における180日の定義
民泊新法(住宅宿泊事業法)では、一般住宅を活用した宿泊サービスを「年間180日以内」という条件付きで認めています。これは単純に「半年間」という意味ではなく、実際に宿泊者を受け入れる「営業日数」が対象です。
具体的には、1月1日から12月31日までの1年間で「人を宿泊させた日数」の合計が180日を超えてはならないという規制です。
つまり、営業していない日や空室の日はカウントされないため、年間を通して効率的に運用すれば、十分な収益を上げることも可能なのです。
具体的な営業日数の数え方と注意点
民泊の営業日数をカウントする際の注意点をいくつか紹介します。
まず、一般的な日数の数え方として例えば、1泊2日の宿泊ならカウントされるのは「1日」です。またチェックインとチェックアウトが同日にあった場合は、その日は「1日」としてカウントされます。
次に、複数の部屋がある場合は「住戸」単位でカウントします。例えば、6部屋あるアパートで1日に3部屋に宿泊者がいた場合、営業日数は「1日」とカウントされます。全ての部屋に宿泊客がいなくても、1部屋でも利用があれば「営業日」としてカウントされる点に注意が必要です。
また、民泊の届出は「住戸」ごとに行うため、複数の物件を所有している場合は、それぞれが別々に180日までの営業が可能です。つまり、複数の物件を所有していれば、全体としての営業日数を増やすことができます。
自治体による追加規制の具体例
注意すべき点として、各自治体が条例で独自の追加規制を設けていることがあります。
| 項目 | 鎌倉市 | 大阪市 | 東京都新宿区 |
|---|---|---|---|
| 種類 | 住宅宿泊事業法(民泊新法)、旅館業法 | 住宅宿泊事業法(民泊新法)、特区民泊(国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業)、旅館業法 | 住宅宿泊事業法(民泊新法)、旅館業法 |
| 営業日数制限 | 住宅宿泊事業法:年間180日以内(特段の上乗せ条例は確認できず) | 住宅宿泊事業法:年間180日以内、特区民泊:営業日数制限なし(365日可)、ただし最低2泊3日以上 | 住宅宿泊事業法:年間180日以内、住居専用地域では月曜正午~金曜正午の宿泊禁止(実質的に週末のみ営業可能、年間約104日程度に制限) |
このような地域ごとの規制は頻繁に更新されるため、最新情報の把握が欠かせません。地域密着型の行政書士は各自治体の最新規制情報を正確に把握、届出のサポートを確実にします。
180日ルールに違反した場合の罰則と注意点

旅館業法違反としての罰則内容
民泊事業を営む際に知っておくべき重要な規制に、年間180日の営業制限があります。この制限を超えて営業した場合、旅館業法に基づき、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。
この罰則は民泊新法(住宅宿泊事業法)ではなく旅館業法から生じるものです。なぜなら、住宅宿泊事業法では「宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数として1年間で180日を超えないもの」を住宅宿泊事業と定義しているからです。つまり、181日目からは法律上、民泊ではなく旅館業となるのです。
このように、民泊事業者は営業日数の管理を徹底することが法令遵守の観点から非常に重要となります。
民泊新法(住宅宿泊事業法)としての罰則
民泊新法(住宅宿泊事業法)自体には、届出義務違反や報告義務不履行に対する罰則は規定されていますが、180日ルール違反に対する直接的な罰則条項はありません。これは、営業日数が181日以上になった時点で、その事業は住宅宿泊事業の定義から外れ、自動的に旅館業法の適用対象となるという法体系の仕組みによるものです。そして、それは無許可での旅館業営業という扱いになってしまうのです。
近隣通報による追加罰則
近隣住民からの通報は民泊事業における最も一般的なトラブル源となっています。特に「騒音問題」「ゴミ分別違反」「不審な出入りの増加」などが頻繁な通報理由として挙げられます。
鎌倉、逗子、葉山といったエリアは特に注意が必要です。これらの地域は静穏な住宅街が多く、比較的富裕層が落ち着いた生活を送るエリアが広がっており、地域コミュニティ活動も活発に行われています。
住民からの通報があった場合、自治体による立入調査が実施され、180日営業制限の確認だけでなく、その他の法令遵守状況(設備基準適合性、標識設置状況など)も綿密に調査されます。複数の違反事項が発覚した場合には、罰則が加重される可能性も高まります。
監視体制と自治体による取り締まり状況
民泊の監視体制は年々強化されています。主な監視方法は以下の通りです:
- プラットフォーム(Airbnbなど)からの情報提供
- 自治体による定期的な立入検査
- 近隣住民からの通報に基づく調査
- インターネット上の広告や予約状況の監視
特に、2019年以降、Airbnbなどの民泊プラットフォームは自治体と協力協定を結び、法令違反の疑いがある物件情報を提供する仕組みが整ってきました。つまり、届出番号なしの掲載や、明らかに180日を超える予約受付などは、容易に発見されるようになっています。
以下に主な罰則の一覧表を示します:
| 違反内容 | 罰則 | 備考 | 該当法律 |
|---|---|---|---|
| 180日超の営業 | 6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金 | 旅館業法違反として扱われる | 旅館業法第10条(無許可営業に対する罰則) |
| 無届営業 | 6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金 | 悪質な場合は業務停止も | 旅館業法第10条(民泊新法には無届営業の罰則条文なし) |
| 標識未掲示 | 行政指導~罰金 | 繰り返しの場合は罰則強化 | 住宅宿泊事業法第73条(標識掲示義務違反) |
| 宿泊者名簿未作成 | 最大30万円の罰金 | 個人情報管理も問題に | 住宅宿泊事業法第76条(宿泊者名簿関連義務違反) |
民泊180日ルールへの対応策・打開策
特区民泊の活用
特区民泊は、国家戦略特別区域内で認められている特例制度で、一定の条件を満たせば180日の制限なく民泊営業ができる制度です。現在、東京都大田区や大阪市などが特区に指定されています。
特区民泊のメリット
- 年間営業日数の制限がない(365日営業可能)
- 住居専用地域でも営業できる場合がある
- 国際的な観光客が多い地域で指定されることが多い
ただし、特区民泊には「最低宿泊日数」(通常2泊3日以上)や、対面での本人確認など、通常の民泊より厳しい条件もあります。また、申請手続きも複雑で、自治体によって要件が異なるため、専門家のサポートが必要です。
特区民泊は東京や大阪など限られた地域が対象となっており、残念ながら2025年4月現在、鎌倉、逗子、葉山では対象となっていません。
旅館業許可(簡易宿所)の取得
180日の制限を超えて営業したい場合、もう一つの選択肢は「簡易宿所」の許可を取得することです。簡易宿所は旅館業法に基づく宿泊施設で、年間営業日数の制限がありません。旅館業として営業できるエリアであればこれが一番おすすめです。
簡易宿所のメリット
- 365日営業が可能
- 宿泊料金設定の自由度が高い
- 「旅館業」としての信頼性向上
許可取得の条件(一例)
- 客室面積が33㎡以上(一部例外あり)
- 玄関帳場(フロント)の設置
- 消防設備(自動火災報知設備など)の設置
- 建築基準法上の用途変更手続き
これらの条件をクリアするには追加投資が必要ですが、長期的に見れば180日の制限なく営業できるメリットは大きいでしょう。行政書士は、物件の現状から最も効率的な改修プランの提案や、消防署・保健所との事前協議のサポートなど、許可取得までの道のりを総合的にサポートします。
マンスリーマンションとの併用区分
もう一つの効果的な戦略は、「民泊」と「マンスリーマンション(30日以上の賃貸)」を組み合わせることです。30日以上の賃貸は旅館業法の適用外となるため、民泊の180日と合わせることで、年間を通じた収益確保が可能になります。
具体的な運用方法
- 繁忙期(例:夏季、ゴールデンウィーク)は民泊として短期宿泊者を受け入れる
- 閑散期はマンスリーマンションとして企業の社宅や研修用として貸し出す
- 年間の営業計画を立て、180日を最大限活用する
この方法のメリットは、投資コストを抑えながら年間を通じた安定収入を確保できる点ですが、1ヶ月以上長期での利用をするケースはそれほど多くはないため、ビジネスとしては難しい場合が多いでしょう。
行政書士による民泊届出サポートのメリット
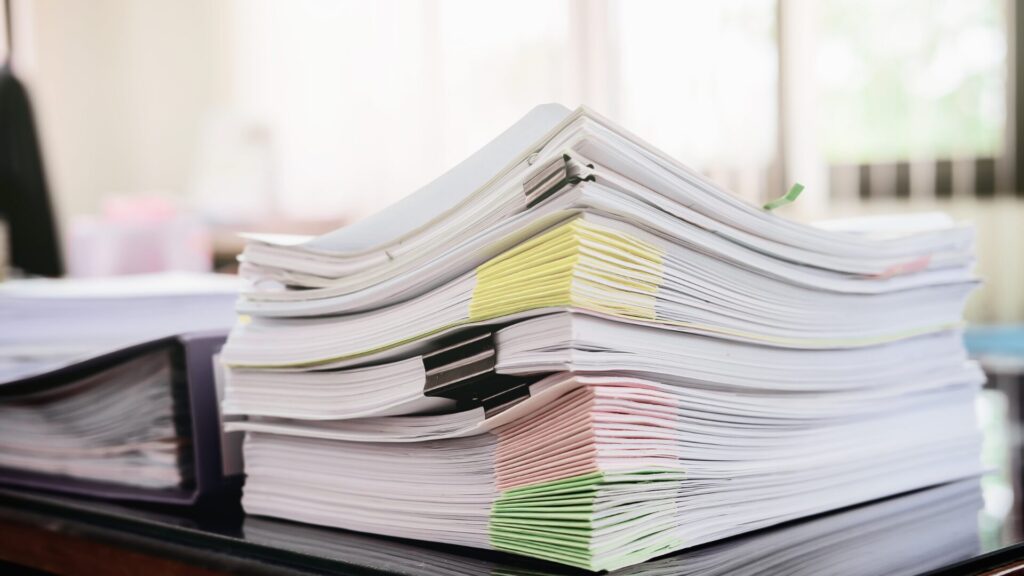
複雑な申請手続きを正確に行うための専門知識
民泊の届出手続きには、「住宅宿泊事業法」だけでなく、「消防法」「建築基準法」「地方条例」など、様々な法令に関する知識が必要です。
届出に必要な書類は多岐にわたり、例えば以下のような書類が必要となります:
- 住宅宿泊事業届出書(法定様式)
- 住宅の図面(間取り、避難経路を記載)
- 設備等の基準適合チェックリスト
- 欠格事由に該当しない旨の誓約書
- 住宅の登記事項証明書
- マンションの場合は管理規約の写しや管理組合の同意書
これらの書類を正確に作成し、不備なく提出することが許可取得の鍵となります。行政書士は各自治体の要求事項を熟知しており、最初から正確な書類を提出することで、審査期間の短縮や追加書類提出の手間を省くことができます。
自治体ごとの規制対応と最新情報の提供
民泊に関する規制は自治体ごとに異なり、頻繁に更新されます。例えば、以下のような自治体ごとの特徴があります。
- 東京都新宿区:住居専用地域では月曜正午~金曜正午の宿泊禁止
- 京都:住居専用地域では1月15日正午~3月16日正午の期間のみ営業可(年間約60日)。
- 葉山町:消防法令やゴミ処理の遵守
民泊を専門に行っている行政書士は常に各自治体の最新情報を把握に努めており、規制変更にも迅速に対応します。
民泊オーナーからよくある質問と回答
-
民泊の届出から営業開始までどのくらいの期間がかかりますか?
-
一般的には、必要書類の準備から届出受理、営業開始まで約1〜2ヶ月程度かかります。具体的な流れは以下の通りです:
- 事前準備(物件確認、必要設備の確認):1〜2週間
- 書類作成:1週間
- 届出提出:1日
- 審査期間:2週間〜1ヶ月
- 準備期間(清掃、写真撮影、登録作業):1〜2週間
私たち民泊専門に行う行政書士にサポートを依頼すると、特に事前準備と書類作成の短縮が期待できます。家主様が忙しくとも、代わりに自治体との協議も行うため、スムーズな届出手続きが可能です。
-
民泊を始めるために、どのような設備が必要ですか?
-
- 消防設備
- 各居室に煙感知器の設置
- 消火器の設置
- 避難経路図の掲示
- 衛生設備
- トイレ・浴室(シャワー可)
- 寝具の定期的な洗濯・交換
- 清掃用具・清掃計画
- その他
- 宿泊者名簿の備え付け
- 外国語による案内表示
- 24時間の緊急連絡体制
これらの基準は最低限のものであり、高評価を得るためには Wi-Fi、充実したアメニティ、キッチン用具なども重要です。行政書士は物件の現状確認を行い、最小限の投資で基準をクリアする方法をアドバイスします。
- 消防設備
まとめ:行政書士に民泊届出を相談するメリット
民泊経営は適切なサポートがあれば、魅力的な副収入源となりうるビジネスです。180日ルールをはじめとする各種規制に対応しながら、最大限の収益を上げるためには、専門家の知見が不可欠です。
当事務所では、鎌倉・葉山・逗子エリアを中心に、民泊届出や簡易宿所許可取得のサポートを行っています。まずは無料相談で、あなたの物件の可能性を一緒に探ってみませんか?