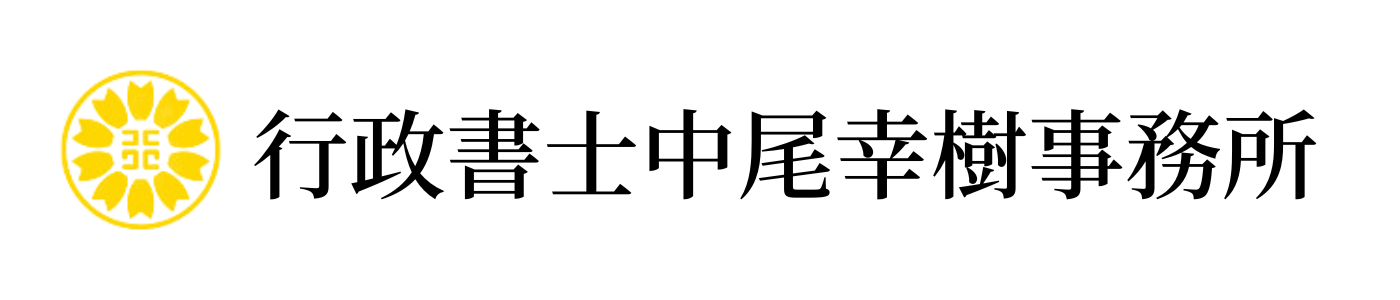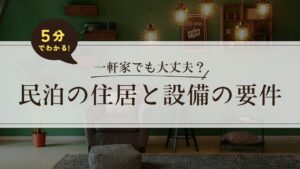投資用物件をお持ちで民泊運営を検討されている方、または自宅の空きスペースを有効活用したいと考えている方にとって、「家主居住型」と「家主不在型」という民泊の2つの形態の違いを理解することは非常に重要です。この2つのタイプは、運営方法や必要な手続き、メリット・デメリットが大きく異なります。
本記事では、会社勤めをしながら副収入を増やしたい方や、初めて民泊運営に挑戦する方にも分かりやすく、家主居住型と家主不在型の特徴や違い、そしてどちらがあなたに適しているかを詳しく解説します。忙しい日常の中でも無理なく始められる民泊運営の形を見つけるお手伝いをいたします。
この記事を読むとわかること
- 民泊新法における家主居住型と家主不在型の定義と基本的な違い
- それぞれの運営形態における法的要件とルール
- 家主居住型と家主不在型、それぞれのメリットとデメリット
- あなたの状況に合った最適な民泊タイプの選び方
- 1. 家主居住型と家主不在型の基本概念
- 1.1. 民泊新法における家主居住型の定義と特徴
- 1.2. 民泊新法における家主不在型の定義と特徴
- 1.3. 民泊新法(住宅宿泊事業法)の基本ルール
- 2. 家主居住型と家主不在型の違いを徹底比較
- 2.1. 居住型と不在型の運営形態の違い
- 2.2. 管理業者委託の必要性
- 2.2.1. 家主居住型の場合
- 2.2.2. 家主不在型の場合
- 2.3. 消防設備など安全基準の違い
- 2.3.1. 家主居住型の場合
- 2.3.2. 家主不在型の場合
- 3. メリット・デメリットから見る最適な選択
- 3.1. 家主居住型のメリットとデメリット
- 3.2. 家主不在型のメリットとデメリット
- 4. 家主不在型民泊運営で知っておくべき重要ポイント
- 4.1. 住宅宿泊管理業者との連携方法
- 4.2. 安全管理と緊急時の対応
- 4.3. 収益性を高めるための運営ポイント
- 5. まとめ
- 5.1. 当事務所の民泊届出サポートについて
- 6. 関連リンク
家主居住型と家主不在型の基本概念

民泊を始めるにあたり、まずは「家主居住型」と「家主不在型」という2つの基本概念を理解しましょう。これらは民泊新法(住宅宿泊事業法)において明確に区分されており、それぞれ異なる要件と運営方法が定められています。
民泊新法における家主居住型の定義と特徴
家主居住型民泊とは、簡単に言えば「住宅の一部を貸し出す形態」です。法律上では、住宅宿泊事業者(民泊のオーナー)が届出住宅(民泊として使用する家)に居住していることが条件となります。
具体的には、住宅宿泊事業者が生活の本拠として使用している住宅で、その一部を宿泊者に提供する形態を指します。たとえば、自宅の空き部屋や離れを宿泊施設として活用するケースが典型的な例です。自宅の2階を民泊として貸し出し、自分は1階に住むというような運営方法も家主居住型に該当します。
家主居住型の重要な特徴は、家主自身が宿泊者を迎え入れ、対面でのコミュニケーションが可能な点です。宿泊者が困ったことがあれば、すぐに対応できる体制が整っています。このため、対面での鍵の受け渡しや、観光案内など、ホスピタリティを重視したサービスを提供しやすいという利点があります。
民泊新法における家主不在型の定義と特徴
一方、家主不在型民泊は「家主が同じ建物に住んでいない形態」の民泊です。アパートやマンションの一室、または別荘など、家主が日常的に居住していない物件を宿泊施設として提供する形態を指します。
法律上では、住宅宿泊事業者(民泊のオーナー)が届出住宅に不在の場合に該当します。具体的には、住宅宿泊事業者が生活の本拠として使用していない住宅、または住宅宿泊事業者が届出住宅から離れた場所に居住している場合が家主不在型となります。
家主不在型の大きな特徴は、オーナーが現地にいなくても運営できる点です。このため、本業を持ちながら副業として民泊経営をしたい方や、遠隔地の物件を活用したい方に適しています。ただし、家主が不在のため、管理面での対応が必要となり、法律上も住宅宿泊管理業者への委託が義務付けられています。
民泊新法(住宅宿泊事業法)の基本ルール
民泊新法、正式名称「住宅宿泊事業法」は、2018年6月に施行された民泊に関する法律です。この法律により、それまでグレーゾーンだった民泊が正式に制度化されました。
民泊新法の基本的なルールとしては、以下の点が重要です。
- 年間提供日数の上限は180日(自治体によってはさらに制限がある場合も)
- 事前の届出が必要(都道府県知事または政令市長への届出)
- 宿泊者名簿の作成・保存義務
- 外国人宿泊者の本人確認義務
- 近隣住民への説明や周知
- 衛生管理や非常時の対応体制の整備
特に家主不在型については、住宅宿泊管理業者への管理委託が義務付けられています。これは、家主が不在であっても、宿泊者の安全確保やトラブル対応ができるようにするための措置です。
民泊新法は、従来の旅館業法とは異なり、住宅を活用した宿泊サービスを前提としているため、比較的参入しやすい制度設計となっています。ただし、地域によっては条例によって営業日や区域に制限が設けられている場合もあるため、開業前には地域の条例も確認する必要があります。
家主居住型と家主不在型の違いを徹底比較
家主居住型と家主不在型は、運営形態や管理方法、設備基準など、さまざまな面で違いがあります。これらの違いを正しく理解することで、自分に合った民泊の形態を選択できます。
居住型と不在型の運営形態の違い
家主居住型と家主不在型では、日々の運営方法に大きな違いがあります。
家主居住型では、オーナー自身が物件に住んでいるため、チェックインの対応やトラブル時の対応を直接行うことができます。宿泊者とのコミュニケーションを重視したホスピタリティあふれるサービスが提供しやすく、地元ならではの情報提供や観光案内なども可能です。例えば、自宅の2階を民泊として運営している場合、チェックイン時には直接ゲストを迎え、鍵の受け渡しや設備の説明をその場で行うことができます。また、何か問題が発生した場合も、すぐに対応することが可能です。
一方、家主不在型では、オーナーが物件に住んでいないため、日常的な管理や宿泊者対応は管理業者に委託することになります。チェックイン・チェックアウトの対応はスマートロックなどのITシステムを活用することが一般的で、非対面での運営が基本となります。例えば、投資用アパートの一室を民泊として運営する場合、スマートロックを導入して暗証番号を事前にゲストに送信し、自動チェックインシステムを構築するといった対応が必要です。清掃やメンテナンスは管理業者に委託し、トラブル発生時も管理業者が対応します。
それぞれの運営形態には一長一短があり、どちらが優れているというわけではありません。自分のライフスタイルや目的に合った形態を選ぶことが重要です。
管理業者委託の必要性
家主居住型と家主不在型では、管理業者への委託の必要性が大きく異なります。
家主居住型の場合
基本的には管理業者への委託は法律上の義務ではありません。オーナー自身が物件に住んでいるため、宿泊者対応や緊急時の対応を自ら行うことができるからです。もちろん、希望すれば管理業者に一部の業務を委託することも可能です。
例えば、予約管理や集客、多言語対応などの一部業務だけを管理業者に委託し、日常的な対応はオーナー自身が行うといった運営方法も選択できます。自分でできることは自分で行い、苦手な部分だけをプロに任せるという柔軟な運営が可能です。
家主不在型の場合
家主不在型は住宅宿泊管理業者への委託が原則、法律上の義務となっています。これは、オーナーが不在であっても宿泊者の安全確保や緊急時の対応ができるようにするためです。住宅宿泊管理業者は国土交通省に登録された正規の事業者でなければなりません。
管理業者に委託する主な業務は以下の通りです:
- 宿泊者の管理(チェックイン・チェックアウト対応)
- 鍵の管理
- 宿泊者名簿の作成・保管
- 周辺地域の生活環境への悪影響防止
- 苦情対応
- 非常時の対応
- 清掃等の衛生管理
管理業者への委託費用は、売上の10~20%程度が一般的で、提供サービスの内容によって異なります。また、一般的にはここから1万〜2万程度の清掃費用がかかります。
消防設備など安全基準の違い

消防設備等の安全面での基準も、家主居住型と家主不在型では異なる点があります。例えば民泊においても火災を知らせる自動火災警報装置の設置義務は免れることができません。両者の違いを見ていきましょう。
家主居住型の場合
基本的には一般住宅と同等の安全基準が適用されます。具体的には、各居室に住宅用火災警報器の設置が必要です。これは一般住宅でも義務付けられているものと同じです。また、消火器の設置も推奨されています。
家主不在型の場合
家主不在型の場合には、居住型と比較してより厳しい安全基準が適用されることがあります。特に、宿泊室の床面積や宿泊者数によっては、消防法上の旅館やホテルに類するものとして扱われ、旅館やホテル同等の消防設備の設置が必要になる場合があります。
例えば、宿泊室の床面積が50㎡を超える場合は、建物用途が「住宅」であっても、厳格な消防設備の設置が求められることがあります。具体的な基準は自治体によって異なるため、事前に地域の消防署に確認することが重要です。
また、旅館業法の「簡易宿所」の許可を取得する場合は、さらに詳細な安全基準が適用されます。これには、非常口の設置や避難経路の確保、防火管理者の選任などが含まれます。
メリット・デメリットから見る最適な選択
家主居住型と家主不在型、それぞれにメリットとデメリットがあります。自分の状況や目的に合わせて、最適な形態を選択しましょう。
家主居住型のメリットとデメリット
家主居住型の最大のメリットは、管理のしやすさと運営コストの低さです。
メリット
- 法的手続きが比較的簡単:不在型に比べて届出手続きが簡素で、管理業者への委託義務もありません。
- 運営コストが抑えられる:管理業者への委託費用が不要なため、収益性が高くなる可能性があります。
- ホスピタリティの提供:宿泊者と直接交流できるため、ローカルな案内など心のこもったサービスを提供できます。これが高評価につながり、リピーターを獲得しやすくなります。
- トラブル対応が迅速:物件に居住しているため、設備の不具合やトラブルにすぐに対応できます。これにより、宿泊者の満足度向上につながります。
デメリット
- プライバシーの制限:自宅の一部を提供するため、自分のプライバシーが制限される面があります。宿泊者と生活空間を共有することになる場合もあります。
- 時間的拘束:チェックインやチェックアウト、問い合わせ対応などで時間的な拘束を受けます。特に仕事が忙しい方には負担になる可能性があります。
- 宿泊者とのトラブルリスク:直接対面するため、宿泊者とのコミュニケーションに問題が生じた場合、精神的ストレスになることがあります。
- スケールの限界:自宅の一部を使用するため、運営規模を拡大することが難しい場合があります。
家主居住型は、自宅の空きスペースを活用して収入を得たい方や、旅行者との交流を楽しみたい方に適しています。特に、時間に余裕がある方や、ホスピタリティを提供することに喜びを感じる方に向いています。
家主不在型のメリットとデメリット
家主不在型は、時間的自由度と事業拡大の可能性が魅力です。
メリット
- 時間的自由度が高い:物件に居住していないため、時間的拘束を受けません。本業との両立がしやすく、会社員の方でも運営しやすい形態です。
- プライバシーが保たれる:宿泊者と生活空間を共有しないため、プライバシーを保ちながら運営できます。
- 物件選択の自由度:居住地から離れた場所でも運営できるため、観光地や需要の高いエリアの物件を選ぶことができます。
- 事業拡大の可能性:複数の物件を運営することも可能で、事業として拡大していける可能性があります。
デメリット
- 管理コストが高い:住宅宿泊管理業者への委託が必須なため、運営コストが増加します。これは収益性に直接影響します。
- 法的手続きが複雑:届出手続きや消防設備など、法的要件が家主居住型に比べて厳しくなることがあります。
- トラブル対応の難しさ:現地にいないため、緊急時の対応や設備トラブルへの迅速な対応が難しい場合があります。
- 地域とのつながりが薄い:地域住民との関係構築が難しく、トラブルが発生した際の対応に苦労することがあります。
家主不在型は、本業と両立しながら副収入を得たい方や、投資用不動産の活用法として民泊を検討している方に適しています。特に時間的制約が多い会社員の方や、物件を複数所有している投資家の方に向いています。
家主不在型民泊運営で知っておくべき重要ポイント
家主不在型で民泊を運営する場合、特に押さえておくべき重要なポイントがあります。これらを理解しておくことで、スムーズな運営と高い収益性を実現できます。
住宅宿泊管理業者との連携方法
家主不在型民泊では、住宅宿泊管理業者への委託が法律で義務付けられています。良い管理業者を選び、効果的に連携することが成功の鍵となります。
まず、住宅宿泊管理業者の選定ポイントとしては、以下の点に注目しましょう。
- 国土交通省の登録を受けていること(登録番号を確認)
- 対応エリアが物件所在地をカバーしていること
- 料金体系が明確であること
- 提供サービスの内容と質
- 緊急時の対応体制
- 実績や口コミ評価
良い管理業者を見つけたら、次は効果的な連携方法を確立します。定期的なコミュニケーションと明確な役割分担が重要です。
例えば、予約管理システムの共有設定、定期的な運営レポートの受け取り、トラブル発生時の連絡体制の確立などが具体的な連携方法となります。また、物件の状態や設備についての情報を詳細に管理業者と共有しておくことで、宿泊者からの質問に適切に対応できるようになります。
管理業者との良好な関係構築は、長期的な運営成功のためにも重要です。単なる業務委託先としてではなく、パートナーとしての関係性を築くことを心がけましょう。
安全管理と緊急時の対応
家主不在型民泊では、安全管理と緊急時の対応体制を整えることが特に重要です。オーナーが現地にいないからこそ、万全の体制を構築しておく必要があります。
安全管理の基本としては、以下の点に注意しましょう:
- 法令に準拠した消防設備の設置(住宅用火災警報器、消火器など)
- 避難経路の確保と避難経路図の掲示
- 非常時連絡先リストの作成と掲示
- 救急医療機関の情報提供
- 宿泊者向け安全マニュアルの整備
緊急時の対応としては、以下のような体制を整えておくことが重要です:
- 24時間対応可能な連絡体制の構築
- 管理業者との緊急時対応フローの確立
- 近隣協力者のネットワーク構築(可能であれば)
- 設備トラブル時の修理業者リストの準備
- 自然災害時の対応マニュアルの整備
例えば、水漏れや停電などの設備トラブルが発生した場合の対応フローを管理業者と事前に決めておくことで、迅速かつ適切な対応が可能になります。また、地震や台風などの自然災害時には、宿泊者の安全確保が最優先となります。避難指示やサポート体制について、管理業者と明確な役割分担を決めておきましょう。
安全管理は宿泊者の命に関わる重要な責任であり、万全の体制を整えることは民泊オーナーとしての基本的な義務です。初期投資としてコストがかかっても、安全設備には十分な投資を行うべきでしょう。
収益性を高めるための運営ポイント
家主不在型民泊の収益性を高めるためには、いくつかの重要なポイントがあります。特に副業として始める場合は、効率的な運営が鍵となります。
【価格設定の最適化】 地域の相場や季節変動を考慮した柔軟な価格設定が重要です。繁忙期と閑散期で価格を変動させることで、年間を通じた収益の最大化が可能になります。また、連泊割引や直前割引など、状況に応じた価格戦略も有効です。
【魅力的な物件づくり】 物件の内装や設備は、予約率に直結します。過度な投資は避けつつも、清潔感と機能性を重視した内装設計が重要です。特に、写真映えするポイントを作ることで、予約サイトでの訴求力が高まります。
例えば、テーマ性のある内装や、地元の特色を活かした装飾など、差別化ポイントを作ることで、多くの宿泊施設の中から選ばれる確率が高まります。
【効果的な集客チャネル】 Airbnbや楽天トラベル、Booking.comなど、複数の予約サイトを活用することで、露出機会を増やすことができます。各サイトの特性を理解し、ターゲットとなる宿泊者層に合わせた掲載内容の最適化が重要です。
【運営効率化のポイント】 チェックイン・チェックアウトの自動化(スマートロックの活用)、清掃サービスの効率的な利用、アメニティの適切な選定など、運営の効率化を図ることで、管理コストを抑えつつ、宿泊者満足度を高めることができます。
【口コミ管理の重要性】 予約サイトでの評価は、新規予約獲得に大きく影響します。宿泊者からの口コミには迅速かつ丁寧に対応し、特に改善要望については真摯に受け止めて対応することが重要です。良い評価を獲得するためには、期待以上のサービスを提供することを心がけましょう。
まとめ
家主居住型と家主不在型、それぞれの民泊形態には明確な違いがあり、メリット・デメリットも異なります。あなたのライフスタイルや目的に合わせて、最適な形態を選択することが重要です。
家主居住型は、管理のしやすさと運営コストの低さが魅力です。自宅の空きスペースを活用して収入を得たい方や、旅行者との交流を楽しみたい方に適しています。一方、家主不在型は、時間的自由度と事業拡大の可能性が魅力です。本業と両立しながら副収入を得たい方や、投資用不動産の活用法として民泊を検討している方に向いています。
特に家主不在型を選択する場合は、住宅宿泊管理業者との連携、安全管理と緊急時の対応、収益性を高めるための運営ポイントを押さえることが重要です。また、法令遵守と地域コミュニティとの良好な関係構築も、長期的な運営成功のカギとなります。
民泊経営は、正しい知識と準備があれば、会社員の方でも無理なく始められる副業の一つです。この記事で解説した内容を参考に、あなたの状況に最適な民泊形態を選択し、充実した民泊経営を実現してください
当事務所の民泊届出サポートについて
当行政書士事務所では、民泊新法(住宅宿泊事業法)に関する届出手続きを全面的にサポートしています。鎌倉・葉山・逗子エリアに精通した専門家が、家主居住型・家主不在型それぞれの特性を理解した上で、最適なアドバイスを提供いたします。
初めての民泊運営で不安をお持ちの方、法令遵守に関する疑問がある方、効率的な運営方法について相談したい方など、どんな段階の方でもお気軽にご相談ください。
お問い合わせはこちらのフォームから、または電話で受け付けております。初回相談は30分無料です。あなたの民泊経営の成功をサポートいたします。
お問い合わせ
関連リンク
- 住宅宿泊事業法(民泊) | 観光政策・制度 | 観光庁 - 国土交通省
- 旅館業法の概要 - 厚生労働省
- 住宅宿泊事業制度(いわゆる民泊)について - 鎌倉市
- 民泊制度ポータルサイト「minpaku」 - 国土交通省