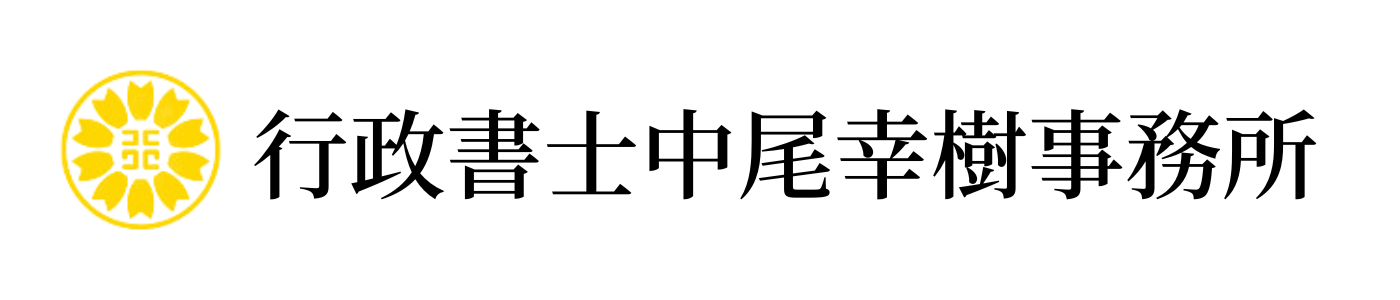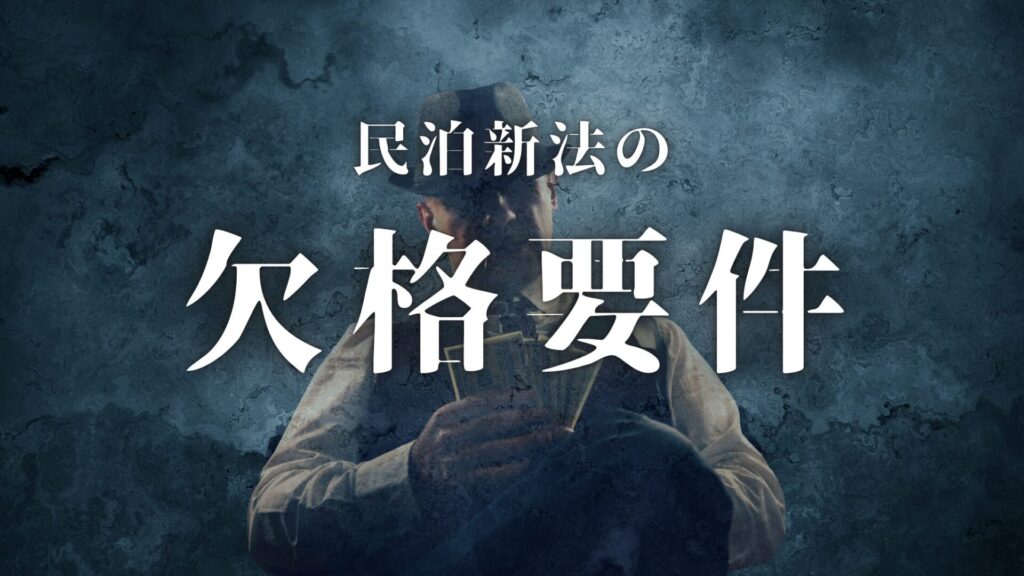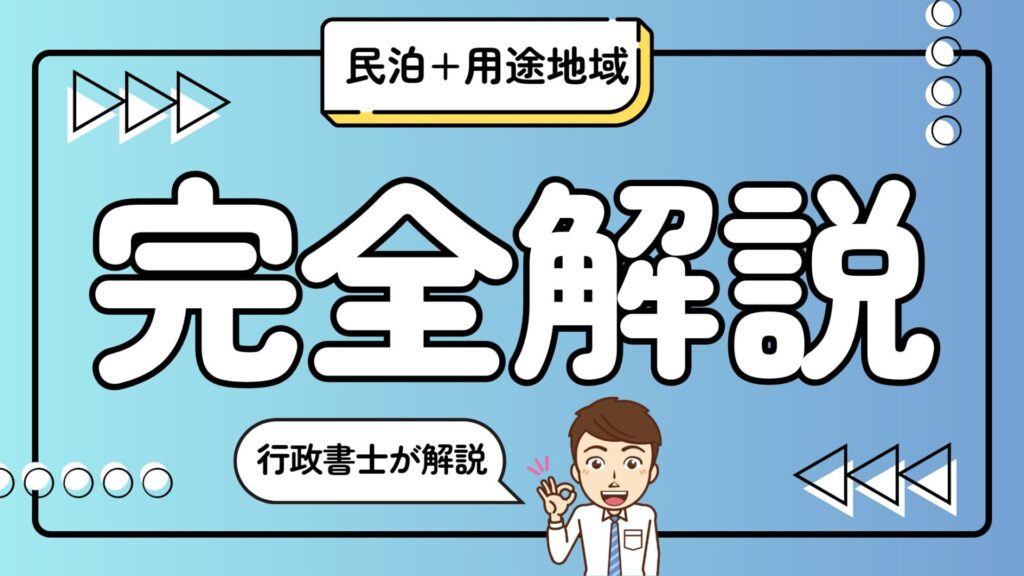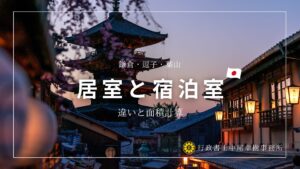\ お気軽にご連絡ください /
\ お気軽にご連絡ください /


はじめに
ゲストハウスや民泊施設の開業を検討している方にとって、簡易宿所営業許可は避けて通れない重要なステップです。しかし、「簡易宿所営業とは何か」「民泊や他の旅館業との違いは?」「どんな手続きが必要なのか」など、疑問や不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。
本記事では、旅館業法に基づく簡易宿所営業について、基礎知識から許可申請の具体的な手続き、運営上の注意点まで、2025年最新の情報を基に徹底解説します。民泊新法との違いや、面積要件(10人以下の場合3.3㎡×定員)などの規制動向も踏まえ、開業に必要な情報を網羅的にお伝えします。
この記事を読むとわかること
- 簡易宿所営業の定義と、ゲストハウス・民泊との関係性
- ホテル・旅館営業、民泊新法との詳細な比較
- 構造設備基準
- 用途地域制限と建築基準法上の注意点
- 許可申請の具体的な流れと必要書類
- 宿泊者名簿作成など運営上の法的義務
- 1. はじめに
- 2. 簡易宿所営業とは?基礎知識を理解する
- 2.1. 旅館業法における簡易宿所営業の定義
- 2.2. 簡易宿所営業の特徴と対象施設
- 2.3. ゲストハウス・民泊との関係性
- 3. 簡易宿所営業と他の宿泊事業の比較
- 3.1. 旅館・ホテル営業との違い
- 3.2. 住宅宿泊事業(民泊新法)との比較
- 3.3. それぞれのメリット・デメリット
- 4. 簡易宿所営業許可の要件・基準
- 4.1. 主な構造設備基準の概要
- 4.2. 申請者の資格要件
- 4.3. 用途地域・建築基準法上の制限
- 5. 簡易宿所営業許可申請の手続き
- 5.1. 申請前の事前準備・相談
- 5.2. 申請の基本的な流れ
- 5.3. 申請から許可までの期間とポイント
- 6. 簡易宿所営業の運営管理義務
- 6.1. 宿泊者名簿作成・衛生管理の概要
- 7. ポイント解説
- 7.1. 違反した場合のリスクと罰則
- 8. 開業に必要な費用と成功のポイント
- 8.1. 申請費用・設備投資の目安
- 8.2. 簡易宿所営業を成功させるコツ
- 9. まとめ:簡易宿所営業許可取得の第一歩
簡易宿所営業とは?基礎知識を理解する
旅館業法における簡易宿所営業の定義
簡易宿所営業は、旅館業法第2条第3項で定められた宿泊営業形態の一つです。法律上の定義では「宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」とされています。
この定義の重要なポイントは「多数人で共用する構造」という部分です。つまり、相部屋形式での宿泊提供が可能な点が、ホテル営業や旅館営業との大きな違いとなります。ただし、必ずしも相部屋でなければならないわけではなく、個室形式での運営も認められています。
旅館業法上、簡易宿所営業は最も柔軟性の高い営業形態として位置づけられており、小規模な宿泊施設運営を始めやすい選択肢となっています。
簡易宿所営業の特徴と対象施設
簡易宿所営業の最大の特徴は、施設規模や設備要件が比較的緩やかである点です。2025年現在の基準では、宿泊定員が10人以下の場合、延床面積は「3.3平方メートル×宿泊定員数」以上あれば良いとされています。例えば、定員5人の施設なら16.5平方メートル以上、定員8人なら26.4平方メートル以上の延床面積が必要です。なお、定員が10人を超える場合は、従来通り33平方メートル以上の延床面積が求められます。
簡易宿所営業の対象となる施設は多岐にわたります。代表的なものとして、ゲストハウス、バックパッカーズホステル、カプセルホテル、山小屋、ペンションなどがあります。これらの施設に共通するのは、比較的低価格で気軽に利用できる宿泊サービスを提供している点です。
また、簡易宿所営業では、共用部分の活用が認められているため、トイレや浴室、洗面所などを宿泊者間で共有することができます。この点も、初期投資を抑えて宿泊事業を始めたい事業者にとって大きなメリットとなっています。
ゲストハウス・民泊との関係性
「ゲストハウス」という言葉は一般的な呼称であり、法律上の定義ではありません。日本でゲストハウスとして営業する場合、多くは簡易宿所営業許可を取得して運営されています。ゲストハウスの特徴である共用スペースでの交流や、ドミトリー形式の相部屋提供は、まさに簡易宿所営業の形態に合致しています。
一方、「民泊」という言葉も法律用語ではなく、一般的には個人が所有する住宅の一部または全部を宿泊施設として提供することを指します。民泊を合法的に運営するには、主に3つの選択肢があります。簡易宿所営業許可を取得する方法、住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づく届出を行う方法、そして国家戦略特区での特区民泊として運営する方法です。
簡易宿所営業として民泊を運営する場合、年間営業日数の制限がないため、本格的な宿泊事業として展開できます。これに対し、民泊新法では年間180日までという営業日数制限があるため、収益性を重視する事業者の多くは簡易宿所営業許可の取得を選択しています。
簡易宿所営業と他の宿泊事業の比較
旅館・ホテル営業との違い
旅館業法では、宿泊営業を「ホテル営業」「旅館営業」「簡易宿所営業」「下宿営業」の4種類に分類されていましたが、平成30年(2018年)6月15日に旅館とホテルが「旅館・ホテル営業」と一つになり現在は「旅館・ホテル営業」「簡易宿所営業」「下宿営業」の3種類に分類されています。それぞれの営業形態には異なる要件が設定されており、事業者は自身の運営スタイルに合った許可を選択する必要があります。
| 項目 | 簡易宿所営業 | ホテル営業 | 旅館営業 |
|---|---|---|---|
| 客室の最低数 | 規定なし | 10室以上 | 5室以上 |
| 1客室の最低面積 | 規定なし(延床面積のみ) | 9㎡以上 | 7㎡以上 |
| 玄関帳場(フロント) | 設置義務なし | 原則設置 | 原則設置 |
| 客室の構造 | 相部屋可能 | 個室のみ | 個室のみ |
| 延床面積要件 | 33㎡以上 (10人以下は3.3㎡×定員) | 規定なし | 規定なし |
この比較表から分かるように、簡易宿所営業は最も柔軟な要件設定となっています。特に客室数の規定がない点は、小規模事業者にとって大きなメリットです。
住宅宿泊事業(民泊新法)との比較
住宅宿泊事業法(民泊新法)は2018年に施行された比較的新しい制度です。簡易宿所営業許可との最大の違いは、営業日数制限の有無にあります。
| 比較項目 | 簡易宿所営業 | 住宅宿泊事業(民泊新法) |
|---|---|---|
| 営業日数制限 | なし | 年間180日以内 |
| 手続き | 許可制 | 届出制 |
| 施設の性質 | 宿泊専用施設可 | 住宅であること |
| 最低面積要件 | 33㎡以上(10人以下は3.3㎡×定員) | 3.3㎡以上/人 |
| 用途地域制限 | あり(住居専用地域は原則不可) | 住居専用地域でも可能 |
民泊では年間180日までしか営業できませんが、簡易宿所営業には日数制限がありません。また、民泊は「住宅」での営業が前提となるため、居住要件を満たす必要があります。一方、簡易宿所営業は専用の宿泊施設として運営できるため、より本格的な宿泊事業に適しています。
手続き面では、民泊新法は届出制であるため比較的簡便ですが、簡易宿所営業は許可制となっており、より厳格な審査があります。
それぞれのメリット・デメリット
| 営業形態 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 簡易宿所営業 | ・客室数の規定なし(1室から開業可能) ・相部屋形式で収益性を高められる ・年間365日営業可能 ・設備要件が比較的緩やか ・共用設備での運営でコスト削減可能 | ・住居専用地域では原則営業不可 ・許可取得に時間と費用がかかる ・旅館業法の厳格な管理義務あり ・用途変更が必要な場合がある ・消防法等の特殊建築物扱い |
| 旅館・ホテル営業 | ・高級感のあるサービス提供が可能 ・個室提供で高単価設定が可能 ・年間365日営業可能 ・社会的信用度が最も高い ・法人向け需要も取り込める | ・最低客室数要件あり(ホテル10室/旅館5室) ・初期投資額が大きい ・設備基準が厳しい ・フロント設置義務でコスト増 ・従業員確保の必要性が高い |
| 民泊新法 | ・届出のみで手続きが簡便 ・住宅での営業が可能 ・初期投資が比較的少ない ・住居専用地域でも営業可能 ・自宅の空き部屋活用が可能 | ・年間180日の営業日数制限 ・収益性に限界がある ・住宅としての機能維持が必要 ・家主居住型は常駐義務あり ・本格的な宿泊事業には不向き |
簡易宿所営業のメリットは、年間を通じて営業できること、相部屋形式での効率的な運営が可能なこと、そして旅館業法に基づく正式な宿泊施設として社会的信用が高いことです。
デメリットとしては、許可取得に時間と費用がかかること、用途地域の制限があることが挙げられます。
民泊新法のメリットは、届出手続きが簡便で住宅での営業が可能な点です。一方、180日の営業制限は大きなデメリットとなり、本格的な事業展開には不向きです。
ホテル・旅館営業は、高級感のあるサービス提供に適していますが、客室数要件があるため初期投資が大きくなります。事業規模や目指すサービス内容に応じて、適切な営業形態を選択することが重要です。
鎌倉で民泊を始めるなら
まずは無料で相談!
簡易宿所営業許可の要件・基準
主な構造設備基準の概要
簡易宿所営業許可を取得するには、旅館業法施行令で定められた構造設備基準を満たす必要があります。2025年現在の主要な基準は以下の通りです。
延床面積については、宿泊定員10人以下の場合は「3.3平方メートル×宿泊定員数」以上、10人を超える場合は33平方メートル以上が必要です。この基準変更により、小規模施設の開業がより現実的になりました。
その他の重要な設備基準として、適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること、宿泊者の需要を満たすことができる適当な数の便所及び洗面設備を有すること、適当な規模の浴室又はシャワー室を有することなどが定められています。
なお、自治体によっては条例で追加の基準を設けている場合があるため、必ず所轄の保健所で確認することが重要です。
申請者の資格要件
簡易宿所営業許可の申請者には、旅館業法第3条に基づく欠格事由に該当しないことが求められます。具体的には、過去に旅館業法違反で許可を取り消された者、禁錮以上の刑に処せられた者などは、一定期間許可を受けることができません。
また、法人が申請する場合は、役員全員が欠格事由に該当しないことが必要です。個人事業主の場合も同様に、申請者本人が要件を満たしている必要があります。
申請者の国籍に関する制限はありませんが、日本に合法的に滞在し、事業を営む資格を有していることが前提となります。
民泊で失敗しないための「欠格事由」完全ガイド:審査に落ちる理由と対策
民泊経営を検討中の方必見!住宅宿泊事業法における「欠格事由」とは何か、審査に通らない理由と対策を鎌倉・葉山・逗子エリアの民泊届出に詳しい行政書士が解説。安心して民泊経営をスタートするための重要知識を提供します。
用途地域・建築基準法上の制限
簡易宿所営業は、都市計画法上の用途地域によって営業可能な地域が制限されています。原則として、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、工業専用地域では営業できません。
ただし、自治体によっては条例で緩和措置を設けている場合があります。例えば、一定の条件を満たせば住居専用地域でも営業が認められるケースもあるため、計画地の用途地域と自治体の条例を必ず確認しましょう。
建築基準法上は、簡易宿所は「ホテル又は旅館」として扱われるため、防火・避難規定などの特殊建築物としての基準を満たす必要があります。既存建物を転用する場合は、用途変更の手続きが必要になることも覚えておきましょう。
【神奈川県】鎌倉・葉山・逗子エリアの民泊経営|用途地域制限を行政書士が徹底解説
鎌倉・葉山・逗子エリアで民泊(住宅宿泊事業)を始めたい方必見!各エリアの用途地域による営業制限や規制を分かりやすく解説。物件選びから届出まで、実務経験豊富な行政書士が成功のポイントをお伝えします。
簡易宿所営業許可申請の手続き
申請前の事前準備・相談
簡易宿所営業許可の申請には、事前準備が極めて重要です。まず、計画している物件が用途地域や建築基準法上の要件を満たしているか確認します。次に、所轄の保健所に事前相談に行き、具体的な設備基準や必要書類について説明を受けます。
事前相談では、建物の登記簿謄本や施設の図面や写真を持参すると具体的なアドバイスを受けやすくなります。保健所の担当者は、地域特有の条例や運用基準についても教えてくれるため、この段階で不明点をすべて解消しておくことが大切です。
消防法や建築基準法の観点から、消防署や建築指導課への相談も並行して進める必要があります。特に既存建物を転用する場合は、用途変更*に伴う改修工事の範囲を早期に把握することが重要です。旅館業は特殊建築物にあたるため通常は建築確認が必要ですが、以下のリンクにある通り一部基準が緩和され、小規模な簡易宿所は手続きが簡素化されています。建築確認が不要であっても建築基準法は変わらずクリアしていないといけません。
外部リンク:建築基 準法改正により 小規模な建築物の 用途変更の手続き|国土交通省2019年改正
申請の基本的な流れ
簡易宿所営業許可申請の基本的な流れは、以下のステップで進行します。
- 事前相談(保健所、消防署、建築指導課)
- 必要な改修工事の実施
- 申請書類の作成・準備
- 保健所への申請書提出
- 書類審査
- 施設の立入検査
- 許可書の交付
申請書類には、営業許可申請書、施設の構造設備を明らかにした図面、法人の場合は定款又は寄付行為の写し、申請者が欠格事由に該当しない旨の誓約書などが含まれます。自治体によって追加書類が必要な場合もあるため、事前に確認が必要です。
申請から許可までの期間とポイント
申請から許可までの標準的な期間は、書類に不備がない場合で1か月程度です。ただし、施設の改修が必要な場合や、追加資料の提出を求められた場合は、さらに時間がかかることがあります。
許可取得を円滑に進めるポイントは、事前相談を丁寧に行い、指摘事項にしっかり対応することです。特に図面については、寸法や設備の配置を正確に記載し、保健所や消防の要求する情報をすべて盛り込むことが重要です。
また、立入検査では、申請書類と実際の施設に相違がないか細かくチェックされます。検査当日までに、清掃や整理整頓を行い、すべての設備が正常に機能することを確認しておきましょう。
簡易宿所営業の運営管理義務
宿泊者名簿作成・衛生管理の概要
簡易宿所営業許可を取得した後は、旅館業法で定められた運営管理義務を遵守する必要があります。重要な義務の一つが、宿泊者名簿の作成と保存です。名簿には、宿泊者の氏名、住所、職業、国籍、旅券番号(外国人の場合)などを記載し、3年間保存することが義務付けられています。
衛生管理面では、客室やリネン類の清潔保持、適切な換気の実施、浴室や便所の定期的な清掃・消毒などが求められます。特に感染症対策として、適切な消毒用品の常備や、体調不良者への対応マニュアルの整備も重要です。
これらの管理義務は、宿泊者の安全と快適性を確保するための最低限の基準です。実際の運営では、より高いサービス水準を目指すことが、リピーター獲得につながります。
POINT
ポイント解説
違反した場合のリスクと罰則
旅館業法に違反した場合、行政処分や刑事罰の対象となる可能性があります。
例えば、無許可営業の場合は6月以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。また、宿泊者名簿の不備や虚偽記載についても、50万円以下の罰金が定められています。
行政処分としては、改善命令、営業停止命令、許可取消しなどがあります。特に許可取消しを受けた場合、一定期間新たな許可を受けることができなくなるため、事業継続に致命的な影響を与えます。
違反を防ぐためには、日常的な管理体制の整備と、従業員への教育が不可欠です。定期的に法令遵守状況をチェックし、問題があれば速やかに改善することが重要です。
開業に必要な費用と成功のポイント
申請費用・設備投資の目安
簡易宿所営業を始めるための費用は、物件の状態や規模によって大きく異なりますが、一般的な目安をご紹介します。
許可申請に直接かかる費用として、申請手数料が2万円から3万円程度必要です。これに加えて、必要書類の作成費用、図面作成費用などで5万円から10万円程度かかることが一般的です。行政書士などの専門家に依頼する場合は、さらに10万円から30万円程度の報酬が必要になります。*当事務所の報酬額について
設備投資については、既存建物の改修費用が最も大きな部分を占めます。消防設備の設置、水回りの改修、客室の整備などで、最低でも100万円から300万円程度は見込んでおく必要があります。新築の場合は、さらに大きな投資が必要となります。
簡易宿所営業を成功させるコツ
簡易宿所営業を成功させるには、明確なコンセプト設定と差別化が重要です。ターゲットとなる宿泊者層を明確にし、その needs に応じたサービスを提供することで、競合施設との差別化を図ります。
立地選定も成功の鍵となります。観光地へのアクセス、公共交通機関からの距離、周辺環境などを総合的に評価し、宿泊者にとって利便性の高い場所を選ぶことが大切です。
また、オンライン予約システムの導入や、SNSを活用した情報発信など、デジタルマーケティングへの取り組みも欠かせません。特に外国人旅行者をターゲットとする場合は、多言語対応や決済手段の多様化も検討すべきでしょう。
まとめ:簡易宿所営業許可取得の第一歩
簡易宿所営業は、比較的少ない初期投資で始められる宿泊事業として、民泊の延長線上としても多くの事業者に選ばれています。本記事で解説した要件や手続きを理解し、計画的に準備を進めることで、スムーズな許可取得が可能となります。重要なのは、法令遵守だけでなく、宿泊者に選ばれる魅力的な施設づくりです。地域の特性を活かし、独自の価値を提供することで、持続可能な宿泊事業を実現しましょう。
【無料相談のご案内】 簡易宿所営業許可の取得をご検討中の方は、ぜひ専門家による無料相談をご利用ください。あなたの事業計画に最適なアドバイスをご提供いたします。
お問い合わせ
おすすめ民泊記事
事業者様必見