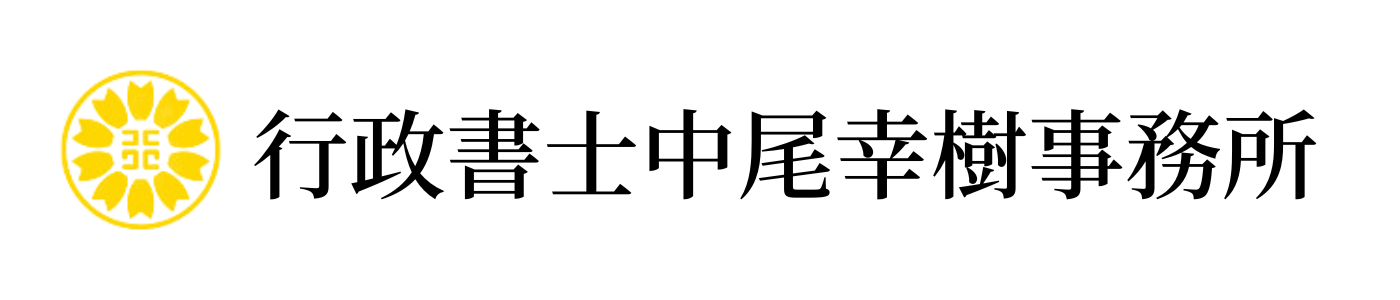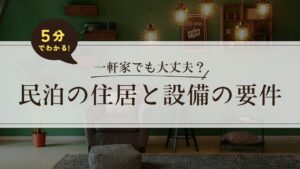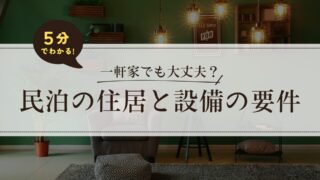
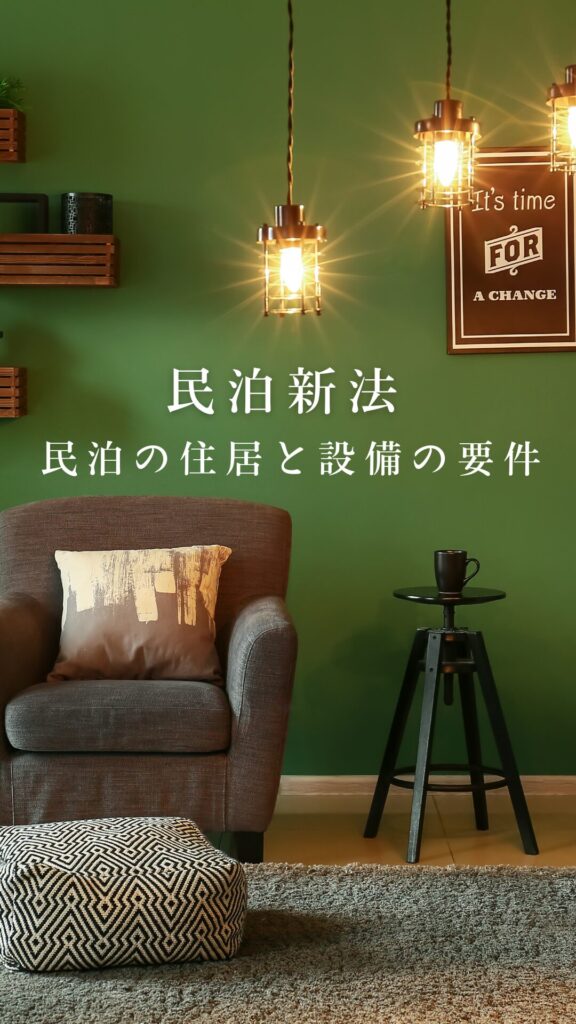
「空いている戸建てを民泊に活用したいけど、何が必要なんだろう?」
このような疑問をお持ちの不動産オーナーの方は多いのではないでしょうか。民泊は収益性が高い一方で、法律上のルールをしっかり理解しておかないと思わぬトラブルにつながることもあります。特に「住宅宿泊事業法(民泊新法)」では、民泊として利用できる「住宅」について明確な定義があり、これを満たさない物件は届出が受理されません。
この記事では、民泊事業を始める際に知っておくべき「住宅の定義」と「設備の要件」について、法律の専門用語を使わずにわかりやすく解説します。
この記事を読むとわかること
- 民泊として届出可能な「住宅」の定義
- 民泊に必要な4つの基本設備とその条件
- 投資用戸建ての民泊活用条件
- 別荘やセカンドハウスの民泊活用方法
- 相続した空き家などを民泊として活用する方法
- 複数の建物を一つの民泊として届け出る方法
民泊新法で定められる「住宅」とは
民泊新法における「住宅」とは、「人の居住の用に供されていると認められる家屋」と定義されています。つまり、人が実際に住んでいる、または住むことを目的とした建物であることが大前提です。
これは一般的な「住宅」のイメージと同じですが、法律上は「設備要件」と「居住要件」の2つを満たしている必要があります。投資用に買ったアパートやマンションでも、これらの要件を満たせば原則、民泊として届出が可能です。
民泊に必要な4つの設備要件
民泊として届出するためには、以下の4つの設備が必要です。
- 台所:調理ができる設備
- 浴室:入浴またはシャワーを浴びられる設備
- 便所:トイレ設備
- 洗面設備:手や顔を洗うための設備
POINT
ポイント解説

1. 設備は独立している
必要はない
例えば、ビジネスホテルにあるような3点ユニットバスのように、浴室・洗面・トイレが一体となった設備でも問題ありません。
それぞれの機能を持っていれば要件を満たします。

2. 設備の仕様に厳しい
条件はない
京都の町家によく見られる「母屋」と「離れ」のように、同一敷地内に複数の建物があり、それらを一体的に使用する権限があれば、複数棟を合わせて一つの「住宅」として届出できます。
例えば、浴室だけが別棟にある場合でも、同一敷地内であれば問題ありません。

3. 公衆浴場などでの
代替は不可
近隣の公衆浴場やコインランドリーなどで代替することはできません。
必ず届出住宅の中に設備が必要です。
民泊の3つの
居住要件
民泊として届出可能な住宅は、以下のいずれかの「居住要件」を満たしている必要があります。
1. 「現に人の生活の本拠として使用されている家屋」
これは、あなた自身や家族が実際に住んでいる家で民泊を行う「家主居住型」の場合です。普段住んでいる自宅の一部を宿泊スペースとして活用するケースが該当します。
住民票がある場所であれば、この要件を満たします。戸建ての一部を宿泊スペースとして活用しながら、自分も同じ建物に住むのがこのパターンです。
2. 「入居者の募集が行われている家屋」
普段は人が住んでいないけれど、賃貸や売却のために入居者を募集している物件も民泊として活用できます。具体的には以下のようなケースが対象になります。
- 実際に入居希望者を募集していることが必要
- 社宅など入居対象者を限定した募集も対象になる
ただし、意図的に相場とはかけ離れた賃料を設定するなどして申し込みされないようにする募集は、「募集のふり」と判断される可能性があり、住宅宿泊事業の届出はできません。
3. 「随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋」
これは別荘やセカンドハウスなど、生活の本拠ではないけれど時々使用する家屋が該当します。この要件はかなり幅広く、以下のようなケースが含まれます:
- 週末だけ使用するセカンドハウス
- 季節ごとに利用する別荘
- 転勤で一時的に空いている自宅
- 相続したが現在は住んでいない実家
- 将来住む予定の古民家
ガイドラインでは「少なくとも年1回以上は使用している」ことが目安とされています。
*投資目的で購入した物件で、オーナー自身が一度も使用したことがない物件は対象外となりますので注意が必要です。
あなたにお勧めの記事
【民泊新法】家主居住型と家主不在型の違いとは?特徴と選び方を徹底解説
民泊経営で迷っている方必見!家主居住型と家主不在型の違いや特徴、メリット・デメリットを詳しく解説。あなたの状況に最適な民泊タイプがわかる完全ガイド。初心者にもわかりやすく解説します。
別荘やセカンドハウスは民泊に活用できる?
結論から言うと、別荘やセカンドハウスも民泊として活用できます。
上記の「3. 随時居住」の要件に該当するからです。
具体的には:
- 年に数回でも実際に使用している
- 所有者自身が使用する権限を持っている
- 生活に必要な4つの設備が整っている
これらの条件を満たせば、使っていない期間を有効活用して民泊として運営することができます。
鎌倉・葉山・逗子エリアは別荘地としても人気があるため、週末は自分で使い、平日は民泊として貸し出すという使い方も可能です。
空き家・相続物件の民泊活用
行政書士として相続や遺言業務に携わっていると、相続した実家や空き家を民泊として活用できるのか、という質問もよくいただきます。
これについても「随時居住」の要件を満たせば可能です。
例えば:
- 相続した実家を将来的に使う予定があり、時々管理のために訪れている
- 転勤で一時的に空いている自宅を、帰ってきた時に住めるようにしておきたい
このような場合、現在は常時住んでいなくても、将来住む予定があり、時々は利用している物件であれば民泊として活用できます。
ただし、居住実体のない新築の民泊専用マンションや、完全に放置されている空き家をそのまま民泊にすることはできません。あくまで民泊は賃貸借物件でも旅館業法上の物件でもなく先の条件に照らし年間180日間の間で有効に活用をするといのが前提です。したがって最低限の設備を整え、オーナー自身も時々利用する事実が必要です。
こちらの記事も人気です
民泊申請の専門家に相談するメリット
民泊の届出を行う際には、上記の要件を理解した上で、各自治体の条例も確認する必要があります。鎌倉・葉山・逗子エリアにはそれぞれ独自の規制がある場合もあり、要件を満たすかどうかの判断が難しいケースもあります。
民泊専門の行政書士へ依頼するメリット
- 物件が法律上の要件を満たしているか客観的な判断が得られる
- 地域の条例や規制について正確な情報を得られる
- 届出書類の作成や申請手続きを代行してもらえる
- 民泊運営に関する実践的なアドバイスがもらえる
特に戸建てを民泊として活用する場合は、収益性とコンプライアンスの両面から検討する必要があります。専門家のサポートを受けることで、安心して民泊事業をスタートすることができるでしょう。
まとめ:民泊として活用できる「住宅」の要件
この記事では、民泊として活用できる「住宅」の条件と「設備の要件」について解説しました。
住宅・設備要件のまとめ
- 「設備要件」:台所、浴室、便所、洗面設備が必要
- 「居住要件」:生活の本拠、入居者募集中、随時居住のいずれか
- 別荘や相続した空き家も、条件を満たせば民泊として活用可能
- 複数の建物を合わせて一つの「住宅」として届出も可能
戸建てを民泊として活用する場合も、これらの要件を満たす必要があります。特に「家主不在型」の場合は、「入居者募集」または「随時居住」の要件を満たすかどうかが重要なポイントとなります。
不明点がある場合は、民泊届出代行や民泊コンサルティングを行っている当事務所にお気軽にご相談ください。物件の状況に合わせた最適な方法をご提案いたします。
※この記事は民泊新法に基づく一般的な情報を提供するものであり、個別の事案については専門家にご相談ください。
※記事の内容は2025年4月現在の法律・ガイドラインに基づいています。
参考:対象となる住宅 | 民泊制度ポータルサイト「minpaku」
お問い合わせ
関連リンク
- 住宅宿泊事業法(民泊) | 観光政策・制度 | 観光庁 - 国土交通省
- 旅館業法の概要 - 厚生労働省
- 住宅宿泊事業制度(いわゆる民泊)について - 鎌倉市
- 民泊制度ポータルサイト「minpaku」 - 国土交通省
民泊の記事
おすすめ