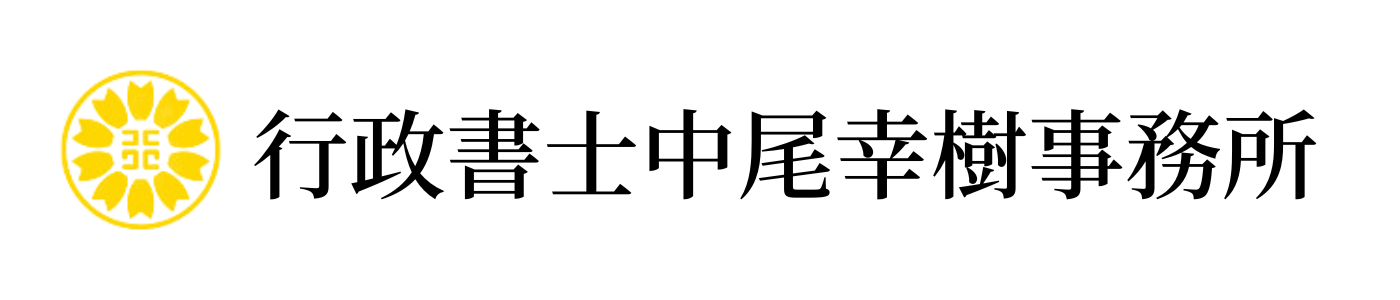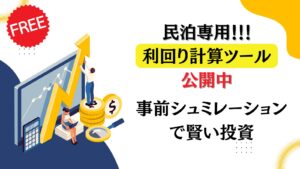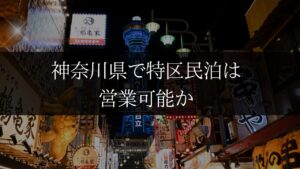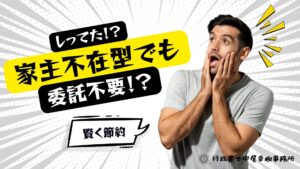\ お気軽にご連絡ください /
\ お気軽にご連絡ください /
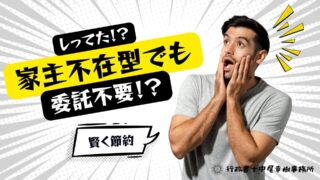
はじめに:なぜ今、住宅宿泊管理業者の講習が注目されているのか
2023年7月の法改正により、住宅宿泊管理業者になるためのハードルが大幅に下がりました。これまで宅地建物取引士や管理業務主任者といった国家資格が必要だった管理業者への道が、わずか28時間の講習受講で開かれるようになったのです。
この変化は、家主不在型で民泊を運営する多くのオーナーにとって大きなチャンスとなっています。なぜなら、管理業者への委託費用は年間売上の20~30%にも及ぶことが多く、自分で管理業者になることで、この費用を大幅に削減できるからです。
特に鎌倉・葉山・逗子エリアで民泊を運営する方にとって、観光需要が高く売上が見込める分、管理委託費用の削減効果も大きくなります。年間300万円の売上がある物件なら、60〜90万円もの費用を節約できる計算になります。
この記事を読むとわかること
- 住宅宿泊管理業者講習の具体的な内容と費用
- 講習の難易度と98%という高い合格率の実態
- 自分で管理業者になることのメリット・デメリット
- 講習申込から登録完了までの具体的な手順
- 民泊届出と管理業者登録を同時に進める効率的な方法
- 1. はじめに:なぜ今、住宅宿泊管理業者の講習が注目されているのか
- 2. 住宅宿泊管理業登録実務者講習の基本情報
- 2.1. 受講要件と費用
- 2.2. 実施機関の比較(民泊向上委員会 vs 全国農協観光協会)
- 2.3. 講習の流れと所要時間
- 3. 登録実務者講習内容の詳細解説
- 3.1. 自主学習(20時間)で学ぶこと
- 3.2. オンライン講義(7時間)会場講義の具体的内容
- 3.3. 修了試験の難易度と合格率(98%の実態)
- 4. 自分で管理業者になるメリット・デメリット分析
- 4.1. 【メリット1】コスト削減効果の具体的な試算
- 4.2. 【メリット2】運営の自由度向上
- 4.3. 【デメリット1】業務負担と責任の増加
- 4.4. 【デメリット2】初期投資と時間コスト
- 5. 講習受講から登録完了までの実務手順
- 5.1. 地方整備局への登録申請手続き
- 5.2. 必要書類と申請費用(登録免許税9万円)
- 5.3. 登録完了までの期間と注意点
- 5.3.1. 「営業所又は事務所」とは何か
- 6. 民泊届出と管理業者登録の同時進行のメリット
- 6.1. 行政書士事務所への依頼タイミング
- 6.2. トータルコストでの最適化提案
- 7. よくある質問(FAQ)
- 8. まとめ:成功する民泊運営のために
- 9. 民泊運営のプロフェッショナルがあなたをサポートします
住宅宿泊管理業登録実務者講習の基本情報

受講要件と費用
住宅宿泊管理業者の講習を受けるための特別な要件はありません。宅地建物取引士や管理業務主任者といった国家資格を持っていない方でも、誰でも受講することができます。
講習費用は実施機関により異なりますが、おおよそ3万5,000円〜4万円程度です。この費用には、20時間の自主学習教材、7時間のオンライン(会場)講義、1時間の修了試験がすべて含まれています。
実施機関の比較(民泊向上委員会 vs 全国農協観光協会)
現在、国土交通省が認定している実施機関は主に2つあります。それぞれに特徴があるので、自分に合った機関を選ぶことが大切です。
民泊向上委員会
民泊に特化した団体として知られています。講習内容も民泊運営の実務に即した内容が多く、実際の運営で役立つノウハウを学べます。料金は3万3000円で、オンラインで試験も受験可能なので全国どこからでも受験可能です。
外部リンク:一般社団法人 民泊向上委員会
全国農協観光協会
農泊・民泊の普及に長年取り組んできた実績があります。地方での開催も多く、都市部以外の方にも受講しやすい環境を提供しています。料金は3万9600円(税込み)となっています。
外部リンク:一般社団法人 全国農協観光協会
講習の流れと所要時間
講習は大きく3つのパートに分かれています。まず20時間の自主学習から始まります。
- (1) 20時間の自主学習
- これはオンラインで提供される教材を使い、自分のペースで進めることができます。期限は設定されていますが、仕事をしながらでも無理なく学習できるよう配慮されています。

- (2) 7時間のオンライン講義又は会場講義
- 民泊向上委員会では自主学習を終えるとオンラインで実務講習を受けられます。
農協観光協会は会場での講義となり講師による解説や質疑応答の時間もあり、疑問点を解消できる貴重な機会です。

- (3) 1時間の修了試験
- 試験はオンラインで実施され、選択式の問題が中心です。修了試験の合格点は80%以上となっており、しっかりと講習内容を理解していれば問題なく合格できるレベルです。

登録実務者講習内容の詳細解説
自主学習(20時間)で学ぶこと
自主学習では、住宅宿泊管理業務に必要な基礎知識を体系的に学びます。主な学習内容は以下の通りです。
住宅宿泊事業法の概要と管理業者の役割について詳しく学びます。法律の条文をそのまま覚えるのではなく、実務でどのように適用されるかを理解することが重要です。
衛生管理や安全確保の具体的な方法も学習します。清掃の頻度や方法、寝具の交換基準、非常用照明器具の設置場所など、実際の運営で必要となる知識を身につけます。
宿泊者名簿の作成方法や本人確認の手順も重要な学習項目です。外国人宿泊者のパスポート確認方法や、オンラインでの本人確認システムの活用方法なども含まれます。
オンライン講義(7時間)会場講義の具体的内容
オンライン講義では、自主学習で学んだ内容をさらに深掘りします。経験豊富な講師陣が、実際の事例を交えながら解説してくれるため、理解が深まります。
特に重要なのが、トラブル対応に関する講義です。騒音問題への対処法、ゴミ出しルールの徹底方法、近隣住民との関係構築など、実務で直面する課題への対応策を学びます。
また、民泊運営における収益性向上のヒントも得られます。稼働率を上げるための工夫や、ゲスト満足度を高める方法など、管理業者として知っておくべきノウハウが詰まっています。
修了試験の難易度と合格率(98%の実態)
修了試験の合格率は98%と非常に高い数字となっています。基準合格点は80%以上に設定されており、講習内容をしっかりと理解していれば合格できる適切な難易度に設定されているためです。
試験問題は主に選択式で、講習で学んだ内容から出題されます。法律の細かい条文を暗記する必要はなく、実務で必要となる知識を理解しているかが問われます。
万が一、不合格となった場合でも、1度に限り再試験の機会が用意されています。追加費用が5,000円程度発生しますが再受験が可能です。
*再受験で不合格となった場合、再度、受講料を支払い研修を再受講する必要があります。
自分で管理業者になるメリット・デメリット分析
【メリット1】コスト削減効果の具体的な試算
最大のメリットは、なんといっても管理委託費用の削減です。具体的な数字で見てみましょう。
年間売上300万円の民泊物件の場合、管理委託費用を20%とすると年間60万円の支出となります。自分で管理業者になれば、この60万円がそのまま手元に残ることになります。
初期投資として講習費用4万円弱、住宅宿泊管理事業者への登録免許税9万円、その他の手続き費用を含めても15万円程度です。つまり、初年度から45万円の利益増加が見込めるのです。
【メリット2】運営の自由度向上
自分で管理することで、運営の自由度が格段に上がります。料金設定の変更、清掃スケジュールの調整、ゲストとのコミュニケーション方法など、すべて自分の判断で決められます。
また、ゲストからのフィードバックを直接受け取れるため、サービス改善のスピードも速くなります。管理会社を通すと伝わりにくい細かなニュアンスも、直接対応することで的確に把握できます。
【デメリット1】業務負担と責任の増加
一方で、すべての業務を自分で行うことになるため、負担は確実に増えます。24時間体制でのゲスト対応、トラブル発生時の迅速な対処、定期的な報告書の作成など、多岐にわたる業務をこなす必要があります。
特に複数の物件を運営している場合、業務量は比例して増えていきます。本業がある方にとっては、時間管理が大きな課題となるでしょう。
【デメリット2】初期投資と時間コスト
講習受講には28時間という時間投資が必要です。また、登録申請の手続きにも相応の時間がかかります。書類の準備、申請書の作成、行政とのやり取りなど、慣れない作業に戸惑うこともあるでしょう。
金銭的にも、講習費用と登録免許税で13万円以上の初期投資が必要です。すぐに回収できる金額ではありますが、まとまった出費となることは確かです。
鎌倉で民泊を始めるなら
まずは無料で相談!
講習受講から登録完了までの実務手順
地方整備局への登録申請手続き
登録実務者講習を修了したら、次は国土交通省の地方整備局への登録申請です。関東地方整備局の場合、さいたま新都心にある事務所で手続きを行います。
申請に必要な書類は法人、個人で異なりますがいずれのばあいでも多岐にわたります。登録申請書、誓約書、略歴書、住民票、身分証明書など、漏れなく準備する必要があります。特に法人で申請する場合は、役員全員の書類が必要となるため、早めの準備が肝心です。
🔗内部リンク:【住宅宿泊管理業関係の申請書類等提出先・問い合わせ先一覧】
必要書類と申請費用(登録免許税9万円)
登録免許税9万円は、申請時に納付する必要があります。収入印紙で納付するケースが多いですが、事前に確認しておくことをお勧めします。
更新の場合には登録手数料が1件当たり19,700円(電子申請だと19,100円)かかります。
その他、住民票や身分証明書の取得費用、郵送費用なども考慮に入れておく必要があります。トータルで10万円程度の費用を見込んでおくと安心です。
登録完了までの期間と注意点
申請から登録完了までは、原則として地方整備局長等に書類が到着した日の翌日から数えて90日かかるとなっています。書類に不備があると、さらに時間がかかることもあるため、慎重な準備が大切です。
登録が完了すると、登録番号が付与されます。この番号は、民泊の届出時に必要となる重要な情報です。大切に保管しておきましょう。
「営業所又は事務所」とは何か
「営業所又は事務所」とは、会社の登記簿などに書かれている場所で、住宅宿泊管理業の仕事を続けて行う拠点として実際に使われている建物のことです。住宅宿泊管理業以外の仕事だけをしている場所は、これに当てはまりません。個人で事業をしていて登記をしていない人の場合は、その人が仕事の中心として使っている場所が営業所又は事務所になります。また、営業所または事務所が実際には使われておらず実体がない場合には必要な体制が整備されているとは言えず認められません。
民泊届出と管理業者登録の同時進行のメリット
行政書士事務所への依頼タイミング
民泊の届出と管理業者登録を同時に進めることで、大幅な時間短縮が可能です。特に行政書士事務所に依頼する場合、両方の手続きに精通した専門家のサポートを受けられます。
最適なタイミングは、講習受講を決めた時点です。講習を受けながら、並行して民泊届出の準備を進めることで、管理業者登録が完了次第、すぐに民泊営業を開始できます。民泊の届出から営業開始までは早ければ1か月程度です。うまくタイムスケジュールを構築しロスのないよう進めましょう。
トータルコストでの最適化提案
行政書士事務所では、民泊届出と管理業者登録をセットで依頼することで、個別に依頼するよりも費用を抑えられることが多いです。また、書類作成の重複を避けられるため、効率的です。
鎌倉・葉山・逗子エリアに精通した行政書士なら、地域特有の条例や規制にも詳しく、スムーズな手続きが期待できます。弊所では民泊届出も行っておりますので、同時にご依頼いただくことも可能です。
よくある質問(FAQ)
-
オンライン講義を欠席した場合はどうなりますか?
-
多くの実施機関で振替受講の制度があります。ただし、追加費用が発生する場合もあるので、事前に確認しておくことが大切です。
-
講習を受ければ必ず管理業者になれますか?
-
講習修了は登録要件の一つです。その他、欠格事由に該当しないことなど、いくつかの要件を満たす必要があります。
-
管理業者登録後に更新は必要ですか?
-
A: 5年ごとの更新が必要です。更新時には、所定の研修を受ける必要があります。また、更新の手数料も必要です。
-
家主居住型でも管理業者登録は必要ですか?
-
家主居住型の場合、管理業者への委託は不要です。ただし、将来的に家主不在型での運営を考えている場合は、先に登録しておくことも可能です。
まとめ:成功する民泊運営のために
住宅宿泊管理業者の講習は、民泊運営のコストを大幅に削減できる大きなチャンスです。98%という高い合格率が示すように、しっかりと準備すれば誰でも管理業者になることができます。
ただし、管理業者としての責任も重大です。ゲストの安全確保、近隣との良好な関係維持、法令遵守など、多くの業務を適切にこなす必要があります。自分で管理するか、委託するか。この判断は、あなたの民泊運営スタイルや、投資できる時間によって変わってきます。まずは講習の内容を理解し、自分に合った運営方法を見つけることが成功への第一歩となるでしょう。
民泊運営のプロフェッショナルがあなたをサポートします
住宅宿泊管理業者の講習受講を検討されている方、民泊届出でお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。
当事務所では、鎌倉・葉山・逗子エリアでの豊富な民泊届出実績を活かし、管理業者登録から民泊届出まで、ワンストップでサポートいたします。
初回相談は無料です。あなたの民泊運営を成功に導くため、最適なプランをご提案いたします。お電話またはメールフォームから、お気軽にお問い合わせください。
【関連リンク】
- 外部リンク:民泊制度ポータルサイト「minpaku」 - 国土交通省
- 内部リンク:民泊の運営と管理方法について詳しく解説
お問い合わせ
おすすめ民泊記事
事業者様必見